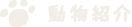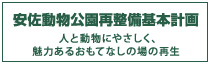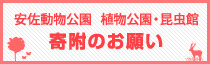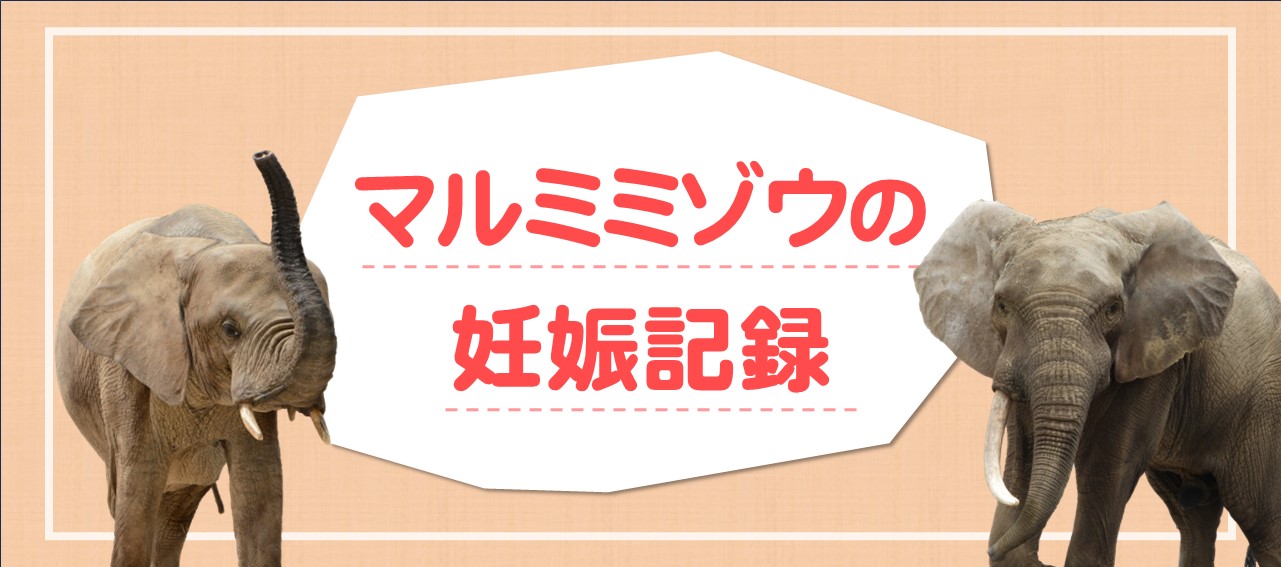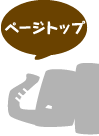2025/01/02巳年:ヘビとヒトの関係を知ってみよう!(前編)
明けましておめでとうございます!
爬虫類担当の じゃい です。今年は1月2日から開園となり、さっそく沢山の方にご来園いただいております。本年も安佐動物公園をどうぞよろしくお願い致します。
さて2025年は巳年ということで、昨年の辰に続いて爬虫類が主役(?)になる1年です。しかし残念ながら、ヘビはお世辞にも人気者とは言えないのが現実...はちゅうるい館に入ることを避けてしまう来園者の方もチラホラいらっしゃいます。
ですが、ヘビって実は私たち人間とはとても関係の深い動物なんですよ!なんたって十二支に選ばれるくらいですからね。 ということで、お正月スペシャルブログ「ヘビとヒトの関係を知ってみよう!」を前後編に分けてお届けしたいと思います。
現在知られるヘビの仲間は4,000種以上。北極圏・南極圏を除いてほぼ世界中に生息しています。そして古来より、ヘビは世界各地で神として崇められる信仰の対象でした。
当時の人たちが特に注目したのが、ヘビの脱皮です。

【脱皮中のボールニシキヘビ】
ヘビを含めた爬虫類の皮膚は硬い角質に覆われているので、古い角質層を脱ぎ捨てないと身体が大きく成長できません。この角質層を脱ぎ捨てるのが『脱皮』という現象なのですが、脱皮するヘビを見た古代の人々は「若返った!」「再生した!」と思ったのだそうです。
そうして、人々はヘビを不老不死や治癒の象徴として崇めるようになりました。ギリシャ神話における医術の神アスクレピオスがもつ杖にも、ヘビが巻きついています。この杖は、古代ローマ帝国のコインにデザインされたり、現在の世界保健機関WHOのシンボルマークとして使われたりしています。

【ヘビが描かれた西暦200年頃のコイン 出典:Hart 1966】
最近は日本でも救急車やドクターヘリの車体に使用されることが増えてきました。古代文明の時代から、脱皮の正体がわかった現在まで、ヘビは人々を救う医療のシンボルとなっています。
その一方で、細長い外見と毒をもつ種がいることからか、ヘビは畏怖・恐怖の対象でもありました。特に聖書においては、エデンの園で禁断の果実を食べるようイヴを唆した誘惑者として描かれており、その正体は邪悪なサタンだとされています。
さらに中世のフランス・イギリス・エストニアなどにおいては、ヘビはカエル・ネコと並んで破門して処刑する対象だとされて、キリスト教徒による駆除が横行していました。毒をもつヨーロッパクサリヘビは特に重要な駆除対象であったのか、現在のイギリスを含めたヨーロッパのいくつかの国では絶滅危惧種となってしまっています。
実際のヘビはとても臆病な動物。こちらから危害を加えたり脅かしたりしなければ、人間を襲ってくることは基本的にありません。ですが現在のイギリスでも、クサリヘビの数が減少する原因の上位に「人間による迫害」が入るのだそうです。まずはヘビに対する人々の理解を深めるため、近年はヘビの保全をテーマにしたイベントも開催されているようです。
【イギリスで行われたヨーロッパクサリヘビ保全のイベント 出典:Kelly et al. 2023】
現在知られている約4,000種のヘビの内、10%以上の470種が絶滅危惧種として国際自然保護連合IUCNのレッドリストに掲載されています。宗教的な駆除は特殊なケースですが、それでも多くは生息環境の破壊や分断など、人間の活動による影響が大きいです。
ネズミや鳥などを食べるヘビは、食物連鎖の上位にいる捕食者であり、小動物が増えすぎないように生態系のバランスを整える役割も担っています。医療のシンボルというだけではなく、実際にヒトを含めた生態系にとって重要な存在です。ヘビを守ることは、私たちの未来を守ることにも繋がっていくんです。
ということで、前編は世界の人々とヘビの関係をざっくりとお話しました。途中に出てきたヘビの脱皮について、詳しく知りたい方は過去のブログ記事も読んでみてくださいね。
明日の後編では、日本人とヘビの関係を見ていきたいと思います。お楽しみに!
じゃい
【参考】
Hart 1966. Ancient coins and medicine. Canadian Medical Association Journal. 94:77-89.
Kelly et al. 2023. Improving attitudes towards adders (Vipera berus) and nature connectedness in primary-age group children. People and Nature. 5: 1908-1921.
三浦 2018. 動物と人間 関係性の歴史学. 東京大学出版会
リリーホワイト 2019. ヘビという生き方. 東海大学出版部
www.reptile-database.org